みなさん、SNSで炎上したことはありますか?
いや、そんな顔しないで。大丈夫、ここでは“燃えた者は救われる”という学部方針です。
私? 7回ほど燃えましたね。うち3回は自覚がなかったのが特徴です。
さて、本講義では、そんな炎上時にほぼ100%出現する言語構造、すなわち「謝罪文」について研究していきます。
具体的には、特に登場頻度が高いあの一文——
「このたびは、ご迷惑をおかけしました」
これ、なぜ全人類がコピペのように使うようになったのでしょうか?
本日はこの言葉の“儀式的意味”と“火消しにおける効果(ほぼゼロ)”について考察していきます。

デタラメ大学 SNS考古学部 炎上資料分析学科 教授。
専門は“デジタル火災史”。
インターネット黎明期、「焼きそば太郎」の名で匿名掲示板に出没。
複数回の炎上と復活を繰り返し、SNS史において“最もスクリーンショットを晒された男”として知られる。
座右の銘は「謝罪文は供物、引用RTは薪。バズとは偶然、炎上は必然。」。
「ご迷惑」って誰に?問題
「ご迷惑をおかけしました」というフレーズ、何がスゴいって、具体性ゼロなんですよね。

- 誰に? → 曖昧(全方位に配慮)
- 何を? → 不明(燃えた内容に触れない)
- なぜ? → 不問(原因を説明しない)
つまりこれは、誰にも謝ってないのに全員に向けて形だけ謝ってるという、高度な回避言語なんです。
もはや社会防御スキルの一種。
心理学的に言えばこれは「感情のワイヤーフレーム構築」と呼ばれ、魂を込めることなく構造だけ提示することで、炎上の火を視覚的にごまかす技法です。
謝罪文テンプレートの系譜
では、この「ご迷惑」構文がどうやって生まれたのか、SNS謝罪文の進化の歴史をざっくり見てみましょう。
プリSNS期(〜2005年)
「マジですいませんでした」「悪気はなかったです…」といった、勢いで謝罪する文化が隆盛を極めました。
- 圧倒的な素直さと口語感
- 文体の雑さ=誠意と見なされた時代
- なぜ謝ってるのかは書いてないが、勢いと語彙の少なさが“本音っぽさ”を演出
- 小規模炎上では効果あり
- ただし「ガキっぽい」「反省してなさそう」と言われたら即延焼
ミクシィ〜ブログ文化期(2006〜2010年)
「不快な思いをされた方がいましたら、申し訳ありません」「あくまで個人の意見でした」といった仮定法逃げ戦略が登場。
- “いたら”構文の台頭(=不快に思ってない人には謝ってない)
- 「個人の意見」盾構文が急増
- 本人なりに丁寧に書こうとして、逆に回りくどくなる傾向
- 誠実そうに見えるが、責任の所在をぼかす構文と見抜かれると再燃
- 「だったら黙ってろ」というブーメラン型反論が頻出
Twitter隆盛期(2010〜2018年)

「ご迷惑をおかけしました。今後このようなことがないよう努めてまいります。」
「軽率な発言でした。深く反省しております。」
といった、見たことある謝罪のテンプレートが広まりました。
- 謝罪文が“定型フォーマット”化された黄金期
- ほとんどが“中身ゼロ”の内容で済まされるようになる
- 「反省しております」+「今後は気をつけます」セット構文
- 炎上の火元から離れた人々には「まあちゃんと謝ってるじゃん」で通る
- だが燃やしたい人々には「誠意がない」と火力ブーストされる危険性あり
🔍進化の注目ポイント
①「ご迷惑」「不適切」「軽率」などの“あいまい語”が大流行
②この頃から「謝罪文を出したこと」そのものが行動としてカウントされるようになる(≒免罪儀式)
動画・AI対応期(2019年〜)
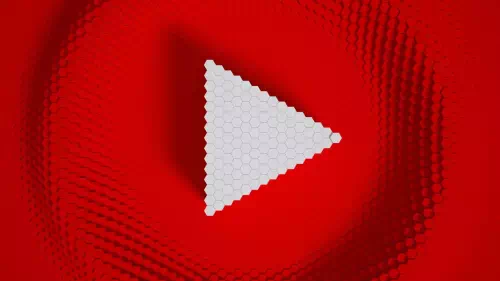
(白背景+スーツ姿で)「このたびは、私の至らなさにより…」
(AI生成)「不適切な表現で不快な思いをさせたこと、深くお詫び申し上げます」
といった視覚的要素が重要になってきます。
- 謝罪動画文化の到来(BGMナシ・無表情・無音・視線ブレあり)
- AI謝罪文ツールの登場により“謝罪文は入力せずとも生成される”フェーズへ
- ついに人間が書かない謝罪文がネット上に出回る
- 冷静すぎて逆に冷たいと叩かれる
- 動画の「手を前で組む動作」が“燃えやすさ増幅ジェスチャー”として定着
AI謝罪文は意味が通じすぎてしまい、逆に「テンプレ感」が露骨に出る
「AIに謝らせるな」という新たな正義感により再炎上
謝罪文 ジェネレーター
2020年代以降、「謝罪文 ジェネレーター」が登場し、
なんとボタン一発でそれっぽい謝罪文が生成できるようになりました。
このたびは私の不適切な発言により、多大なるご迷惑をおかけしました。
今後は発信に細心の注意を払い、信頼回復に努めてまいります。
もはや本人が書いていないことすらある。
しかし——問題はここからです。
誰も読んでいない。スクショされて晒されて終わり。
謝罪文とは、書いた瞬間に“証拠”であり“墓碑”になるんですね。
“本当に反省している”構文の限界
ときどき見かける“心から謝るタイプ”の謝罪文。
「私の至らなさが招いた結果であり、弁解の余地もございません」
これ、一見誠実そうに見えるけど、火が消えません。むしろ強まります。
なぜか?
答えは簡単。

まるで「おかわり自由」の焼肉店。
“反省”を提示した時点で、「じゃあ次は人格まで焼きましょうか?」というコースが始まるのです。
なぜ具体的に謝ると燃えるのか?
ここで興味深い事例を紹介しましょう。
あるインフルエンサーが、「不適切な発言」とせず、ちゃんと発言内容を謝罪文に書いたところ、その一文が再拡散されて新たな炎上が始まりました。
はい、そうなんです。
SNSでは「何に謝ってるかを明記する」=新しい火種を提示するという意味を持ちます。
消そうとして薪を投げ込むという、高度な逆効果演出です。
つまり最強の謝罪文は、「読む気を削ぐ戦術」こそが正義なのです。
- 具体的には言わない
- 感情にも触れない
- 長くて読みづらくする
教授として、私が炎上した話(1つだけ)
さて、ここで実例として私の体験談を1つ。
私が某SNSで「バズってる人に嫉妬するのは自然なことです」と書いたところ、「お前の器の小ささが見えた」と引用RTされ、あれよあれよと燃えました。
仕方なく出した謝罪文がこちら:



「私の不用意な投稿により、ご迷惑をおかけしました。今後は発言に留意いたします。」
……うん、見事に何も言ってない。けどこれが最適解なんです。
【まとめ】“謝罪”は消火ではなく、儀式である
本講義の結論は以下の通りです。
- SNSの謝罪文は、意味のある言葉よりも、燃えにくい言葉が重視される
- 「ご迷惑をおかけしました」は万能テンプレであり、お守りでもある
- 誠実すぎると燃える。曖昧に逃げると冷える。不条理? 当然です。
みなさんも炎上のときはぜひ、本文の意味を曖昧にした長文を用意してください。
それが一番、燃えにくいとされています(当学科調べ)。
🧪 補論:現代SNSにおける“高性能謝罪文”の条件
私・火叢焼の10年にわたる観察研究(主観)により、現代における謝罪文に求められる性能は次の5つに集約される。
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| ① 具体性ゼロ | 内容に触れないことが最大の防御 |
| ② 長文である | 炎上民が読まない程度に長くする |
| ③ 反省感を出すが、謝っていない | 「反省してます」が主語 |
| ④ 今後の決意で締める | 「努めてまいります」で余韻を演出 |
| ⑤ スクショされても“つまらない” | 再拡散時に燃えにくい構造が必要 |
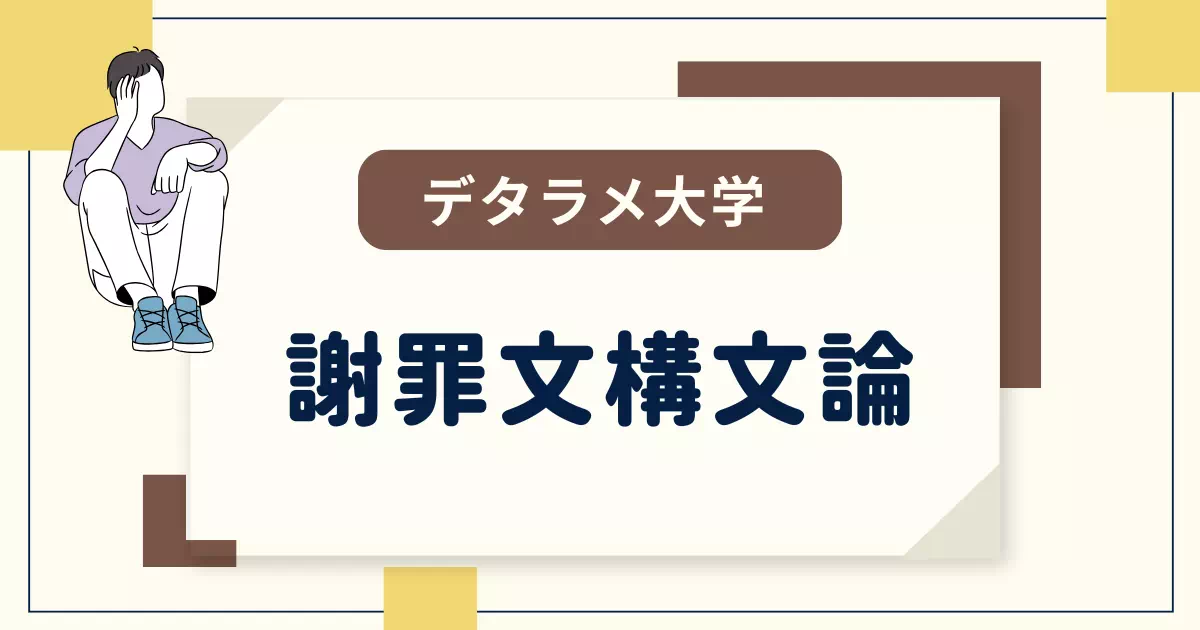


レポート(コメント)提出